
安全に入浴するために
 |
ヒートショックを防ぐために
寒暖差を少なくしましょう

|
脱衣所や浴室内を暖めてから入浴しましょう。
浴室に暖房設備がない場合は、シャワーから給湯したり、お風呂が沸いたらよくかき混ぜて蒸気を立て、ふたを外しておくことで暖めることができます。
浴槽に入るときは、心臓から遠い足先から肩まで少しずつお湯をかけて、お湯の温度に体を慣らすようにして、足からゆっくりと浸かりましょう。
お風呂から出る時も、急がず、ゆっくり移動する方が体温の急激な変化を防ぎます。
また、温まったからだが冷えないようにしましょう。
|
湯温はぬるめに
つかる時間は10分

|
熱いお湯が好きな方でも、温度は41度以下にしましょう。37度から39度程度の湯が、身体の緊張がやわらいでリラックスできると言われています。
熱いお湯に長時間浸かると汗が出て脱水症状を引き起こす危険もあります。
お湯につかる時間は10分までを目安にしましょう。
温度計やタイマーなどあると便利です |
脱水に注意しましょう
 |
入浴前と入浴後には水やカフェインの入っていない麦茶などを飲みましょう。
脱水症状は体内の水分不足によって、必要な体液が減少することでおこります。特に高齢者は、脱水症状になりやすいので注意しましょう |
浴槽から急に立ち上がらない |
入浴中には体に水圧がかかっています。
急に立ち上がると体にかかっていた水圧がなくなり、圧迫されていた血管が一気に拡張して、脳に行く血液が減って貧血のような状態になり、意識を失ってしまうことがあります。浴槽から出るときは、手すりや浴槽のへりなどを使ってゆっくり立ち上がるようにしましょう。 |
食事、飲酒、薬服用
 直後の 直後の
入浴は避けましょう
|
高齢者は、特に、食後に血圧が下がりすぎることがあるため、食後すぐの入浴は避けましょう。
飲酒は、一時的に血圧が下がるのでアルコールが抜けてから入浴しましょう。
体調の悪いときや、精神安定剤、睡眠薬などの服用後も入浴は避けましょう。 |
入浴時間も考えて |
入浴中、湯舟から立ち上がれなくなったり、具合が悪くなったり事故があるかもしれません。
事情が許せば、夜間よりも、医療機関に対応してもらえる時間帯の入浴のほうが安心です。
早く発見してもらうことも大切なので、ご自分一人で入浴できる場合でも、ご家族にひと声かけてから入浴するようにしましょう。
|
浴室の環境を整える
  |
滑りやすい浴室内での転倒を防ぐために、バスマットや手すりを設置したり、段差を解消する、滑りにくい材質の床にする、お風呂の間口を広くするなども大切です。
入浴チェアやバスボード等入浴補助具もありますので活用しましょう。
|
体調が悪い時は無理をしない
 |
体調不良を感じたら、無理な入浴避けましょう。
特に、発熱や血圧の異常、胸の痛みなどの症状がある場合、からだに大きな負担が掛かります。
入浴が出来ない時には、湯を張った洗面器などに足だけつける「足湯」はいかがでしょうか。
爽快感やリラックス効果、血行促進効果が期待できます。 |
 入浴介助 入浴介助
 |
①からだの変化に注意しましょう
皮膚の赤み、発疹などからだの異常は、裸になる入浴のときに発見しやすいものです。 異変があったら治療につなげましょう。 異変があったら治療につなげましょう。
②安全第一を心がけ、転倒等には十分に気をつけましょう。
高齢者が転倒すると骨折などの大怪我になることもあります。
転倒リスクを最小限に抑るよう、動作のサポートをしましょう。
③入浴前には
トイレを済ませましょう。
浴室内に石鹸やシャンプーなど必用なものを準備しておきます。
しっかりと準備しておくことで、入浴中の無駄な動作が減り、転倒のリスクを減らせます。
④高齢者がひとりで入浴できる場合は
「時間が長い」「音が全くしない」「突然大きな音がした」
など何か異常を感じたら、ためらわずに声を掛けましょう。
⑤入浴を嫌がるときは
まず高齢者の話をゆっくり聞きましょう。
体力的な問題、億劫、寒いから服を脱ぎたくない、安全に対する不安、お湯の熱さが不快
などの理由があります。
認知症で衣類の脱ぎ着や入浴の手順がわからなくなっている場合や
うつ病などが隠されている場合もあります。
不安を少なくなるように言葉をかけ、入浴補助具なども利用して安全対策をしましょう。 |

入浴の効果
 |
血液循環が良くなります
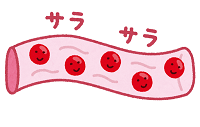

免疫力アップ、疲労回復
|
血液は、二酸化炭素や疲労物質、老化物質などいらないものを回収し、酸素、栄養分、ホルモン、免疫物質など必用なものを運ぶ役目をしています。
入浴で温まると血管が拡がり血液の循環が良くなり心臓の動きも強くなります。
すると新陳代謝が活性化、免疫力もアップして感染症などの疾患にかかりにくくなります。
疲労の原因である老廃物を排出し、リラックスして良い睡眠がとれるので疲労回復効果があります。
|
 むくみがとれます むくみがとれます |
長時間立っていると重力にしたがって足に血液などが溜まりやすく、それがむくみにつながります。
お湯に浸かると水圧によって全身がマッサージされたような状態になり、溜まっている血液の流れを心臓に戻すことができ、むくみがとれます。 |

こりがほぐれ関節が柔軟になります |
水の中では、からだが軽く感じますね。
(体重が10分の一くらいの感じ)
それは、下から引っ張る力(重力)から解放されるためで、関節や筋肉への緊張がゆるみます。
筋肉のこりがほぐれ、関節の柔軟性が高まります
痛みも緩和される効果もあるようです。 |
からだの汚れを
洗い流します
  |
からだに有害な物質や微生物、いらなくなった皮脂などを洗い流すので、細菌や菌が増えるのをおさえ、皮膚の感染症や、湿疹、化膿などの皮膚トラブルを防ぐことができます。
角質が柔らかくなり、保湿効果が高まります。
尿路感染症などの泌尿器系の疾患もの予防にもなります。
定期的な入浴は、健康を守り、感染症から身を守ります。 |
運動療法効果
  |
浮力は下から引っ張る力(重力)を減らしますが、逆に水には粘性・抵抗作用があり、水中でからだを動かすと、陸上の約3倍から4倍の負荷がかかります。
湯舟に入ったり出たりする動作、手足を動かすことなどでも、運動療法と同じ効果があります。 |
リラックス効果
  |
高齢者にとって、入浴は日常的に取り入れやすいストレス解消法の一つです。
あたたまることでリラックスできます。
お風呂に浸かる時間は、衣服を身に着けない非日常的空間で心とからだが開放的になり疲れが和らいでリフレッシュできます。 |

